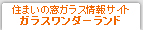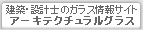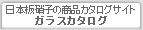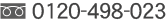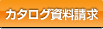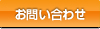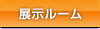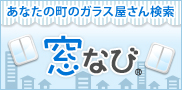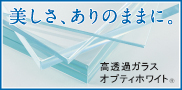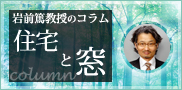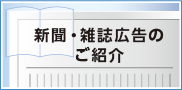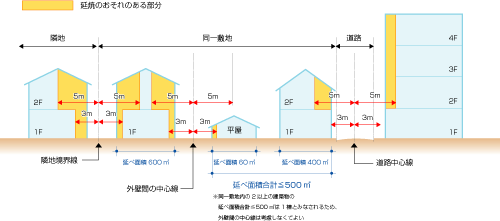都市部は、住宅が非常に密集しています。そのような地域で、もしも火災が起こったら、被害は周囲へ大きく広がります。火災現場において特に恐いのが、密集地域での延焼です。
そのような隣家への延焼を防ぐ対策として、法律(建築基準法)が定められています。都市部の密集地帯を、「防火地域」または「準防火地域」として指定し、安全対策が義務づけられています。また、延焼によって被害を拡大させないために、開口部を防火戸にするなど、防火設備を設けなければなりません。
木造建築物の多い日本の市街地は、常に火災の危険性があります。
そこで、都市の防災のために、重要な地域を「防火地域」及び「準防火地域」と定め、建築物の構造等を規制して、延焼の危険を抑止しています。
市街地の火災を防除するため都市計画法第9条に基づき、各市町村で下記の種類の地域が定められています。
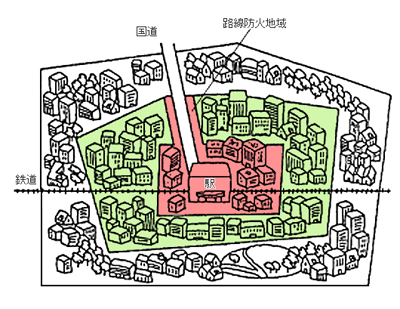
【引用】(社)カーテンウォール・防火開口部協会
| 街の中心部、主として商業地域に指定されることが多い。 | |
| 防火地域を取りまき、比較的防火上重要な地域が指定されます。 |
防火地域、準防火地域内においては、一定の大きさを越える建物を「耐火建築物」または「準耐火建築物」としなければなりません。
| 階数 | 延べ面積(S) | 建築物の構造制限 | 適用条項 |
|---|---|---|---|
| ≦2階 | S≦100㎡ | 耐火建築物、または準耐火建築物 | 建築基準法 第61条 |
| S>100㎡ | 耐火建築物 | ||
| ≧3階 (地階を含む) |
- | 耐火建築物 |
【引用】月刊「建築知識」2008年1月号54ページ
※上記以外に各市区町村で決められた地域がありますのでご確認ください
| 延べ面積(S) | 建築物の構造制限 | 適用条項 |
|---|---|---|
| S≦50㎡ | 平屋の附属建築物で、外壁・軒裏が防火構造の場合 | 建築基準法 第61条1号 |
|
建築基準法 第61条3号・4号 |
|
| 卸売市場の上家・機械製作工場で主要構造部が不燃材料の場合 | 建築基準法 第61条2号 |
|
【引用】月刊「建築知識」2008年1月号54ページ
| 階数 | 延べ面積(S) | 建築物の構造制限 | 適用条項 |
|---|---|---|---|
| ≦2階 (地上階数) |
S≦500㎡ | 制限なし ただし、木造建築物等で外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分は防火構造 |
建築基準法 第62条第1項 |
| 500㎡<S≦1500㎡ | 耐火建築物、または準耐火建築物 | ||
| S>1500㎡ | 耐火建築物 | ||
| =3階 (地上階数) |
S≦500㎡ | 耐火建築物、準耐火建築物、または、令136条の2に規定する木造3階建ての技術基準に適合する建築物 | |
| 500㎡<S≦1500㎡ | 耐火建築物、または準耐火建築物 | ||
| S>1500㎡ | 耐火建築物 | ||
| ≧4階 | - | 耐火建築物 |
【引用】月刊「建築知識」2008年1月号54ページ
※上記以外に各市区町村で決められた地域がありますのでご確認ください
| 延べ面積(S) | 建築物の構造制限 | 適用条項 |
|---|---|---|
| 卸売市場の上家・機械製作工場で主要構造部が不燃材料の場合 | 建築基準法 第61条2号 | |
【引用】月刊「建築知識」2008年1月号54ページ
防火地域または準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で「延焼のおそれのある部分」に、「防火戸」などの防火設備を設けなければなりません。
これらは建築基準法第64条に定めれられています。
延焼に関しては、隣接している2つの建築物の間の距離が重要となってきます。建築基準法第2条第6号には、「延焼のおそれのある部分」として、危険性のある建築物間の距離を定義しています。
※「延焼のおそれのある部分」=「隣接している建築物の外壁間中心線からの距離が、1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建築物の部分」
ただし、防火上有効な公園、広場、川や、耐火構造の壁などに面する部分は除きます。
| ≫ パイロクリア | ≫ パイロペア | ≫ パイロストップ | ≫ クロスワイヤー、菱形ワイヤー |